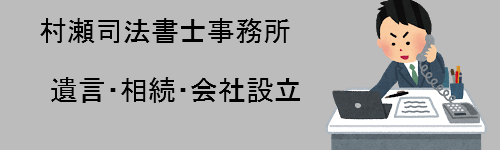「認知症」の疑いのある親が書いた「遺言書」に疑問があるとき、どうしたら良いですか
特定の相続人に対して多額の遺産を残す親の遺言書 (自筆証書遺言) が見つかる場合があります。少額の遺産しか相続できない相続人としては不満が出るところです。遺言書作成の当時、親に「認知症」の疑いがあった場合、親の面倒を見ていた相続人が自分に有利となる遺言書を書かせたとの疑いも出てきます。このようなときどうしたら良いのでしょうか。

まずは、相続人で話し合いをしてみることです。話し合った結果、色々な疑念が晴れて納得できる場合もあります。また、親が認知症であったことを認めた場合は、親の遺言を無効なものと考えて、相続人全員で遺産分割協議をすることもできます。
しかし、あくまで親の認知能力に問題はなく、遺言書は有効であると主張する相続人がいる場合は、簡単には決着できません。親の認知能力を巡って遺言書の有効、無効を争うことになります。

(「遺言能力」とは )
遺言を有効に作成するためには、遺言者に「遺言能力」があることが必要です。民法には遺言能力について「15歳以上であること」「事理弁識能力を有すること」等の形式的なことしか定められていません。どの程度の精神能力が遺言書を書くことのできる実質的な能力であるか明確な定めはありません。
学者の間では、遺言書を作成するには、遺言を理解するに足りる判断能力が必要であるとされています。そして、この判断能力は、作成する遺言書の難易度に応じて変わり得るものだと考えられています。
例えば、複雑な条件を付けた遺言であるとか高度な金融知識を必要とする遺言書などを作成する場合は、要求される判断能力は高くなります。「全財産を長男に相続させる」などの簡単な遺言であれば、その内容が理解できる程度の判断能力があれば良いことになります。

(「遺言無効確認請求訴訟」とは )
相続人間で話し合いの決着が付かない場合は、裁判で決着するしかありません。遺言の有効性に疑問のある相続人が紛争の解決を求めて裁判所に提訴することになります。具体的には、遺言書の有効性に疑問のある相続人等が原告となって「遺言無効確認請求訴訟」を起こします。被告となるのは、相続人、受遺者、遺言執行者などです。この場合、被告となる相続人は全ての相続人を被告とする必要はなく遺産を承継した相続人のみを被告とすることができます。
この裁判で遺言書の無効が確認された場合は、遺言書は無効となり、残された親の遺産は相続人全員による「遺産分割協議」で分割されることになります。但し、遺言書で紛争化している関係上、すんなりと遺産分割協議がまとまる可能性は少ないと思います。遺産分割協議を巡って新たな「遺産分割調停」や「遺産分割審判」という裁判手続きに進んでいく可能性が高くなります。

( 裁判所での「遺言能力」の判断方法 )
裁判所では、遺言者の判断能力を次のような3つの段階を踏まえて判断します。
① 「医学的な観点から認知症の疾患状況の確認」
裁判所は、まず医学的判断を基礎として認知症の疾患状況を確認します。遺言者が生前に病院などで受けた検査結果等があれば、それを基に認知症の進行度合い(軽度、重度など)を判断します。
認知症の検査方法としては、「長谷川式簡易知能評価スケール」「MMSE」等が参考にされると思います。その他、認知症の判断材料になる資料や証言があれば参考にします。
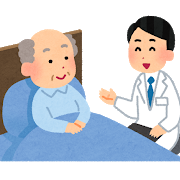
② 「事理弁識能力の欠如の状況確認 」
遺言者の事理弁識能力が欠けていると判断される場合、その状態が常時か否かが確認されます。認知症の初期段階では、正常に近い時と判断能力が低下している時が交互に現れることがあります。いわゆる「まだらボケ」という状態です。
常時、事理弁識能力が欠けている場合、裁判所としては、遺言書は「無効」と推認します。推認とは、裁判の相手方より反対の証拠が出されない限り、認定するということです。遺言が有効であると主張するには、遺言書作成時は、たまたま事理弁識能力が備わっていたことを立証する必要があります。例えば、遺言書の作成に立ち会った医師の証言などです。
③ 「進行途上または軽度の認知症の場合 」
医学的判断として、遺言者の認識能力が常時障害を生じさせるものではないような症状の場合、遺言書を作成したとき遺言者の認識能力で遺言の内容が理解できるかどうかが確認されます。
当然、遺言書の中身の複雑度合いとも関係してくることになります。原告・被告双方が自己に有利となる証拠を提出して争うことになります。
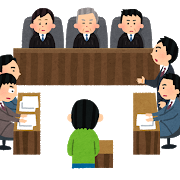
いづれにしても、裁判所は医学的な所見だけで単純に遺言書の有効無効を判断するのではなく、遺言書作成当時の状況を詳しく見た上で総合的に判断するということになります。
(まとめ)
認知症には、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症などがあります。発症する認知症の種類によって症状や特徴も異なっています。
裁判で争いになる場合は、本人は既にいませんので、残された資料や関係者の証言を基に争われることになります。病院の診断カルテ、介護施設での介護日誌、ケアマネージャーの訪問記録など重要な証拠資料となります。
相続人間の話し合いの場でも、それらの客観的な資料があれば、それらを基に冷静に話し合いをすれば、裁判にまで行かずに相続人間で円満に解決できるかもしれません。