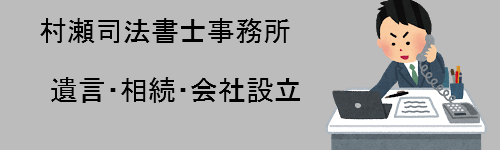認知症ぎみの高齢者は「遺言」をすることができますか
相続が発生し「遺言書」がある場合、遺産分割は遺言書に従って実施されます。しかし、遺言書の内容に納得のいかない相続人から、「遺言書作成当時、遺言者は既に認知症になっていた。こんな遺言書を作成できるわけがない。」と主張される場合があります。相続人間で調整がつかなければ、納得のできない相続人から「遺言無効確認の訴え」を提起され、泥沼の裁判闘争に発展する可能性があります。

このような状況を未然に防ぐ意味で認知症ぎみの高齢者が遺言書を作成する場合は慎重に行う必要があります。過去の裁判例から見ると遺言者が認知症だからといって一律に遺言書が無効とされるわけではありません。軽・中程度の認知症の方が作成した遺言書を有効とした裁判例も多く見られます。しかし、認知症の進んだ方の遺言書は無効と判断されるリスクが高いため注意が必要になります。

遺言書の作成を困難にする認知症などの精神上の障害の存否は、病名だけで画一的に判断されるものではありません。例えば、認知症の診断ツールである「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」(30点満点で20点以下は認知症の疑いあり)の点数だけで自動的に判定されるものではありません。他者とのコミュニケーション能力や自己の置かれた状況を把握する能力がある場合は、点数が低くても遺言書を作成する能力があると判断される場合があります。
そこで、認知症ぎみの高齢者が遺言書を作成する場合の考慮すべきポイントについて整理しておきます。
(1) 遺言書を作成できる能力のあったことの証拠を収集しておく。
「HDS-R」の点数が20点以下だから遺言書を作成できないわけではありません。遺言書を作成するに当たって重要な点は「遺言者が自己の財産の状態と範囲を認識し、遺言の内容と効果を理解しているか。」です。さらに、他者とのコミュニケーション能力や自己の置かれた状況を把握する能力があったかどうかもポイントになります。

これらの能力のあったことを証明できる証拠資料を遺言書作成段階で収集しておくことです。具体的には、医療機関や介護施設との接点があれば、主治医、看護師、ケアマネ、介護担当者などが作成したカルテ、看護記録、介護日誌、要介護認定のための資料の写し、等が考えられます。遺言書作成時のビデオ撮影も有効だと思います。公正証書で遺言書を作成しておくことも対応策の1つとなります。
(2) 認知症の程度に応じて遺言書の内容の複雑性を調整する。
遺言書作成に必要とされる能力は、遺言書自体の内容の複雑さに応じて変わってきます。遺言書の内容が複雑であれば、それを理解する高い能力が必要になります。認知症の程度が進んでいる場合は、本人が理解できる範囲の簡単な遺言内容にする必要があります。
例えば、「自宅は妻に、預金は長男に、株は長女に相続させる」のような内容の簡単なものです。これに色々な持分割合や条件などを付けたりすると理解が難しくなります。

但し、内容が単純であったとしても結果が重大なものについては、慎重に判断する必要があります。例えば、「すべての財産を孫に遺贈する。」のように内容的には単純で理解しやすいものであっても、本来の相続人である妻や子供を差し置いて孫に全てを渡す内容の遺言は結果の重大性の面で、簡単だから良いとは言えません。合理的な理由を用意しておく必要があります。
(3) 遺言内容と遺言者のこれまでの行動や言動が矛盾していないこと。
遺言書の内容が、遺言者のこれまでの行動や言動から見て合理的であることが必要です。遺言の動機や理由、遺言者と相続人とのこれまでの関係性や遺言に至る経緯などから考えて遺言書の内容に齟齬(そご)がないことが必要になります。

これまで長く反目してきた長男に対して、「長男に全て相続させる。」とする内容の遺言では、合理的な理由がないと遺言書の有効性に疑問がでます。合理的な理由を遺言書自体に簡単に書いておくことも必要になります。
遺言書は多くの場合、高齢者が作成します。そして高齢者であれば一定レベルの能力の低下(老化現象)は見られます。それが認知症レベルなのかどうかは人によりますが、ある程度の能力低下は当然の摂理です。ですから、高齢者の作成した遺言書について亡くなってから「無効だ」と言われないように十分注意して作成する必要があります。
.png)
(まとめ)
遺言書は遺言者が亡くなった後の「争族」問題を回避する為の手段として作成されることが多いと思いますが、遺言者の認知能力を巡って「争族」問題に発展する場合があります。このような本末転倒の状態にならないよう高齢者の遺言書の作成については慎重に対応して頂く必要があります。