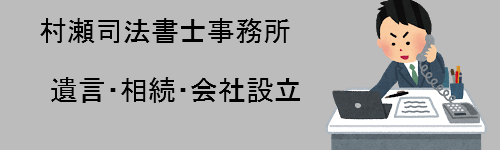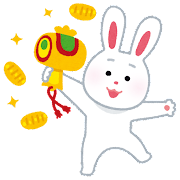「死因贈与」契約で配偶者名義の自宅を確実に相続できますか
終活の相談の中で「自宅などの財産を配偶者から確実に相続できる方法はないのですか。」という質問があります。一番確実な方法は「生前贈与」という方法があります。しかし、自宅などを生前贈与すれば多額の「贈与税」などの税金が発生するため、お勧めできないことが多いと思います。但し、婚姻期間が長い夫婦の場合は、生前贈与に特別の減税措置があるのでこれを活用することができます。

<「生前贈与」-おしどり贈与の活用- >
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、一定の要件を満たせば、基礎控除額110万円の他に最高2,000万円までの控除を受けることができます。いわゆる「おしどり贈与」と言われるもので週刊誌などで時々特集されています。
2,110万円の贈与税の非課税枠は魅力的ですが注意点があります。まず、「相続」であれば課税されない不動産取得税が課税されます。また、不動産の名義変更登記で必要な登録免許税の税率が相続に比べて高くなります。(贈与2%、相続0.4%) さらに、夫婦間の相続の場合、1億6,000万円までは相続税がかからないので、例えば、夫名義の自宅を妻が相続しても、多くの場合、相続税はかかりません。
そのため、「おしどり贈与」の適用にあたっては、税金面の損得計算を正確に行って判断する必要があります。多くの場合「相続」まで待った方が得となることが多いと思います。

<「相続」まで待つ >
相続により取得する場合は税金面で有利になることが多いと思います。また、「小規模宅地特例」などの減税措置の特例も相続による取得の場合は利用することができます。しかし、相続であれば相続人全員による「遺産分割協議」が必要になり、自宅の取得について確実性がありません。子供達が自宅の相続に異論を唱えていなければ良いのですが不安があります。
生前には異論がなくても、いざ相続が発生すると異論が出る場合も多いのです。自宅の居住権だけの確保であれば、新しい制度である「配偶者居住権」を活用して問題解決が図れる場合があります。しかし、自宅の所有名義にこだわるのであれば、「相続」まで待っていたのでは遅いことになります。
<「遺言書」を書いてもらう -遺贈の活用- >
次の手として、「遺言」の作成が考えられます。これを「遺贈」といいます。「自宅不動産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を書いてもらえば良いことになります。公正証書遺言にしておけば、さらに確実性が高いものとなります。

但し、確実性という意味では不安がないとは言えません。公正証書遺言と言えども作成してから内容の変更や撤回が自由に行えるからです。公正証書で作成した遺言の内容を自筆証書で撤回することもできます。相続関係者が別の遺言書を本人に書かせるかもしれません。遺言書は、最後に作成したものが最終の意思として優先されます。
心配し過ぎの面はありますが、遺言では確実に相続できる保証はありません。
<「死因贈与」契約の活用 >
そこで、より確実性を求める場合は「死因贈与」契約を活用することになります。死因贈与契約は、その名の通り「契約」ですので、配偶者間で契約書を作成して合意します。「自分が亡くなったら自宅を配偶者に贈与する」という内容の契約書に双方が署名捺印して合意します。

「契約」は、本来、一方当事者が勝手に契約内容の変更や撤回をすることは許されません。しかし、「死因贈与」については、判例によって、「遺贈」に準じて、贈与者の最終の意思を尊重する観点から贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています。
そのため、「死因贈与」契約をする場合は、予め自宅不動産に「仮登記」を入れておきます。これにより、一方的な撤回を実質的にしにくくすることができます。自宅不動産を確実に取得する方法として、「死因贈与」契約は有効な方法だと思います。
「仮登記」の内容は、少し専門的になりますが「始期付所有権移転仮登記」を行います。これは、配偶者の生存中は自宅の所有権は配偶者のものですが、配偶者が亡くなると所有権が相手方配偶者に移るというものです。
但し、単純な「死因贈与」契約の場合、仮登記をしても撤回が絶対できないわけではありません。死因贈与契約を撤回して、仮登記を抹消すれば撤回したことになります。手続き的に相当面倒ですが撤回はできます。
そこで、さらに確実にするためには、「負担付き死因贈与契約」とする方法があります。例えば、自宅に配偶者の母親が同居している場合、母親の面倒を見る代わりに自宅を贈与するというものです。つまり、何らかの負担の見返りに贈与をするという契約内容にするのです。負担がついているので負担付き贈与契約と言います。

負担の内容は自宅を取得する対価として相応の内容であることが必要ですが、負担を履行した場合は、贈与契約を自由に撤回できなくなります。ここまでやれば確実に自宅を相続する(正確には死因贈与を受ける)ことができます。
< 贈与契約書 作成上の注意点 >
◆ 契約書は公正証書で作成した方が良い。
後々の契約内容の疑義の発生を防ぐと同時に、登記手続をスムーズに行うことができるからです。
◆ 契約書の内容として「執行者」を定めておくと良い。
通常は、もらう側の配偶者を執行者に指定しておきます。こうすれば、不動産の登記手続きの際に亡くなった配偶者の相続人の協力なしに登記することができます。
◆「 持ち戻し免除 」の定めを書いておくと良い。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合は必要ありませんが、20年未満の夫婦の場合は書いておいた方が良いと思います。例えば、次のような条項案となります。「第×条に定める贈与について、夫は妻に対して夫の相続に関して、その持ち戻しを免除する」 贈与契約書の最後のあたりに記載しておけば良いでしょう。
被相続人(亡くなった配偶者)から死因贈与や生前贈与によって特別に受けた利益のことを「特別受益」といいます。特別受益は、その贈与がなければ本来は相続財産であったはずの財産であると考えることができます。
特別受益に相当する財産の額を相続財産に加算して、相続財産とみなして計算する法律上の取り扱いを「持ち戻し」といいます。特別受益の持ち戻しを計算することによって、相続人の相続分を実質的に平等とすることができます。
この「持ち戻し」を残された配偶者については免除するというものです。贈与された自宅は遺産分割協議上は相続財産にカウントせずに計算できるというものです。当然、残された配偶者の取り分(相続分)が多くなるということです。
◆ 「遺留分」について十分留意する必要がある。
生前贈与であれ死因贈与であれ、残された他の相続人の遺留分を贈与によって侵害することはできません。自宅を贈与されることによって他の相続人の遺留分を侵害する恐れがある場合は、必要な事前対策を講じておく必要があります。
例えば、「遺留分相当額の財産は他で確保しておく」「遺留分相当額の一時払いの生命保険に入っておく」などがあります。遺留分を不当に侵害する内容の贈与であれば、不満のある相続人から「遺留分侵害額請求」が残された配偶者になされる恐れがあります。
(まとめ)

今回は、確実に自宅不動産を相続(生前贈与を含めれば相続ではありせんが)で確保する方法を検討しました。残される相続人の人間関係が良好で家族関係が円満な場合は、このような方法は必要ないと思います。
しかし、中には対策が必要な場合もあると思います。そのような場合は今回の内容も1つの参考にして下さい。