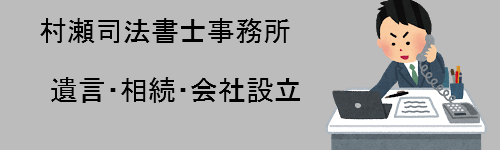成年後見人の選任方法が「親族後見人」優先へと大転換の気配
平成31年3月18日、最高裁判所は、「後見人には身近な親族を選任することが望ましい。」とする考え方を示しました。これは従来の裁判所による成年後見人選任の考え方を大きく転換する画期的な内容となっています。
認知症等で判断能力が不十分となった方の生活を支える成年後見制度は、これまで色々な取り組みが実施されてきており、紆余曲折を経ながら、徐々に普及、拡大が図られてきました。
制度発足当初は、世の中の認知度も低く、制度の普及はあまり進みませんでした。しかし、急速な高齢化と認知症罹患者の増加により、成年後見制度は世の中に急速に普及し、最近では世間の認知度も非常に高いものとなっています。

当初、後見人は被後見人に最も身近な親族が選任されていました。親の後見人は息子や娘が選任されていました。親族後見人は、被後見人にとって最も身近な存在であり、後見人にとっても親の生活を親身に支えることができ両者の利害が一致すると考えられていました。

ところが、親族後見人による財産の横領や私的流用事件が多発するようになり、裁判所としても親族を後見人に選任することに迷いが生じてきました。被後見人は認識能力が十分でなく、親族による財産の不正使用は外からは容易に発見することができません。不正が発見された時には財産は殆んど残っていないようなケースも見られるようになってきました。
このような状況の中で、後見人を選任する責任を負った裁判所は、後見人を法律専門家である弁護士や司法書士から選任するようになっていきました。裁判所としても選任した後見人が不正を働けば任命(選任)責任を問われかねないことから、法律の専門家を後見人に選任するようになりました。その結果、専門職後見人の数は徐々に増えて行きました。
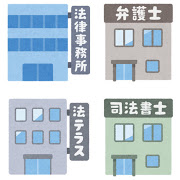
そして、一定程度の財産がある場合や財産の管理運営が難しいと予想されるケースは、親族よりも専門職後見人を優先して選任する運用スタイルが徐々に定着してきました。その結果、現在では親族後見人は減少の一途となり、弁護士や司法書士が選任されるケースが一般的となってきました。
このような過去の経緯を踏まえて、今回の最高裁判所による見解の発表は大きな変革をもたらすものと言えます。
今回の転換をもたらした要因として考えられることは、色々あると思います。
1つは、専門職後見人が前提となると専門職への報酬が継続的に発生する為、後見人の選任申立を躊躇(ちゅうちょ)するケースが増えていることです。結果として制度利用件数が伸び悩んでしまっていることです。本来、必要とされている方への制度の利用促進が図られないことが大きな転換の要因と考えられます。
また、成年後見人の不正を未然に防止する仕掛けが色々と工夫されてきている点です。大口の財産は、信託銀行に預け入れ、出し入れには必要なチェックが働く仕組みが最近導入されました。これにより、後見人による財産の不正使用をある程度防止することができるようになりました。
さらに、後見人は、親族が親身になって行うことが本来的な姿であり、一部の不正な輩(やから)が悪いことをしたからと言って、大部分の真面目な親族の方による後見制度を否定すべきではないという考え方も底流にはあると思います。
このような背景から国は2017年に制度利用促進の計画を策定し、見直しに着手してきました。そして、利用者が制度のメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁判所は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明しました。従来、最高裁判所がこの種の問題に見解を述べることはありませんでしたが、今回の発表となりました。今年1月に各地の家庭裁判所にこの内容を通知したということです。
具体的には、最高裁判所は基本的な考え方として、「後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい。」と提示しました。また、後見人の交代についても、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとしました。
昨年6月から今年1月にかけて、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論も重ね、考えを共有したといいます。

今回の制度変更は、具体的にどのような運用になるかは今後の状況を確認する必要がありますが、従来、諦(あきら)めていた親族後見人の選任がより容易になることは間違いないと思われます。今後の運用の変化を注視したいと思います。